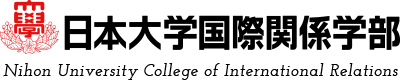カリキュラム

国際総合政策学科Department of International Studies
カリキュラム
国際関係の基礎から、現代の国際問題に関わる先端領域まで、幅広く学び知識を深められます。2年次からは、さらに分野分けした講義を受講することで、より理解が深まります。
1年次 カリキュラム
| 共通科目 | 全学共通教育科目 |
|
|---|---|---|
| 基礎科目 |
|
|
| 総合教育科目 |
|
|
| 外国語科目 |
|
|
| 地域研究 |
|
|
| 専門外国語 |
|
|
| 観光外国語 |
|
|
| 健康スポーツ科目 |
|
|
| 専門基礎科目 |
|
|
| 情報 |
|
|
| 学部共通科目 | 資格外国語 |
|
| 特別教育 |
|
|
| 日本語教員養成科目 |
|
2年次 カリキュラム
| 共通科目 | 演習 |
|
|---|---|---|
| ジャパンスタディーズ |
|
|
| 地域研究 |
|
|
| 専門外国語 |
|
|
| 観光外国語 |
|
|
| 情報 |
|
|
| 学科共通専門科目 | 国際関係コース コース専門基礎 |
|
| 国際関係コース コース専門 |
|
|
| 国際ビジネスコース コース専門基礎 |
|
|
| 国際ビジネスコース コース専門 |
|
|
| グローバルスタディコース コース専門基礎 |
|
|
| グローバルスタディコース コース専門 |
|
|
| グローバル観光コース コース専門基礎 |
|
|
| グローバル観光コース コース専門 |
|
|
| 学部共通科目 | 資格外国語 |
|
| 留学生用演習(交換留学生) |
|
|
| 日本語教員養成科目 |
|
3年次 カリキュラム
| 共通科目 | 演習 |
|
|---|---|---|
| ジャパンスタディーズ |
|
|
| 地域研究 |
|
|
| 専門外国語 |
|
|
| 観光外国語 |
|
|
| 学科共通専門科目 | 国際関係コース コース専門 |
|
| 国際ビジネスコース コース専門 |
|
|
| グローバルスタディコース コース専門 |
|
|
| グローバル観光コース コース専門 |
|
|
| 学部共通科目 | スポーツ交流 |
|
4年次 カリキュラム
| 共通科目 | 演習 |
|
|---|---|---|
| 学科共通専門科目 | 国際関係コース コース専門 |
|
| 国際ビジネスコース コース専門 |
|
|
| グローバルスタディコース コース専門 |
|
|
| グローバル観光コース コース専門 |